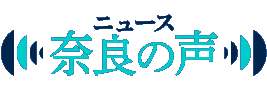ワシやタカの仲間であるクマタカ(角鷹)は世界的にも数が少ないため保護鳥として環境省レッドデータリストの絶滅危惧Ⅰ類(絶滅の危機にひんしている種)に指定されている。
体長は約75センチ。成鳥は顔面が真っ黒で頭部には冠羽があり、背面は茶褐色。喉から腹部にかけては白色で、黒褐色の縦斑が多数みられる。翼や尾羽根には黒帯があり、翼を広げると約165センチ以上もある雄壮な大型の猛禽(もうきん)だ。
日本では全国各地に生息し、山地から亜高山帯の落葉広葉樹林や針葉樹林でウサギやテン、ネズミなどの哺乳類やヤマドリ、キジなどの鳥類、ヘビ、トカゲなどの爬虫(はちゅう)類を獲物とし生活している。
私たちの住む奈良県で主にクマタカが観察されるのは、スギやヒノキなどの人工林が広がっている吉野地域の山間部だ。過去には樹林や伐開地上空を旋回し獲物を探すクマタカの姿が、しばしば見かけられたものだ。
しかしこの地域は、昨年9月に近畿地方南部を襲った台風12号の影響で、崖崩れや土砂崩れが各地で発生し、数多くの死傷者が出たばかりか国道が寸断され、地滑りによって山の地形は大きく変わってしまった。おそらくこのような状況下では、クマタカをはじめ多くの生き物たちにも被害が生じ、環境の変化が生活を著しく脅かしているのではないだろうかと危惧される。
今後道路が復旧し土砂が取り除かれた後は、環境調査を行い、被害の実態を把握する必要があるのではないだろうか。また、従来、経済的な観点からスギやヒノキだけを多く植樹してきたが、成長した木材を出荷しても採算が合わないなどの理由から、間伐や枝打ちなど山の管理がおろそかになり、土砂崩れが起こりやすい状況にあったのではということなども、破壊された山林を再生する際には考慮すべきである。
そして、今後植林される樹木はブナやクヌギ、コナラなど広葉樹も含めた植樹を選定し、より自然林に近い混合林を形成し、土砂崩れの起こりにくいような状態に改善すべきではないかと考える。さらに、基本的にこれからの自然再生は、私たち人間の都合だけを考えるのではなく、生き物たちにとっても豊かな森を構築し、人と自然が共生する環境をつくり上げていくことが大切ではないだろうか。
近い将来、被害に遭った地域の人々の生活が復興し、豊かに生まれ変わった吉野の森の上空を、生態系の頂点に君臨するクマタカが優雅に旋回する姿を、もう一度見てみたいものである。
◇
生駒市在住の野鳥写真家・与名正三さんによる連載。県内の自然環境の変化を、そこにすむ鳥の姿を通して考える。毎月第2、4月曜に更新予定。
与名さんの写真集を正価より安くお求めいただけます
◇奈良高山の自然 茶せんの里の生きものたち(東方出版)
◇森のハヤブサ ナニワの空に舞う(東方出版)
→ ご案内はこちら