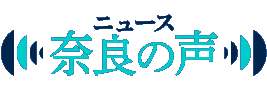近畿地方が本格的な梅雨に入る6月中旬。大きな河川やため池近くのヨシ原(ヨシはアシの別称)から「ギヨギヨシ、ギヨギヨシ」と夏の暑さに拍車をかけるようなやかましい野鳥のさえずりが聞こえてくる。オオヨシキリだ。
オオヨシキリは夏鳥として渡来し、北海道から九州までの川や湖沼、休耕田などのヨシ原で繁殖する。体長は約18センチ。頭部から背面にかけオリーブ色がかった淡い茶褐色。腹部は淡いクリーム色で脇の部分が灰褐色の地味な野鳥だ。
繁殖期は巣の近くのヨシに止まり縄張りを宣言するため、盛んにさえずる。巣はヨシを束ねた場所にヨシの葉を使ってコップ状のものを作る。卵は3~4個で、抱卵から15日ほどでひなが誕生するが、巣立ちまではさらに2週間ほどの日数がかかる。
このオオヨシキリの仲間で、色彩や容姿がそっくりなのがウグイス。体長約16センチ。オオヨシキリよりもやや小さい。頭部から背面にかけてはオオヨシキリよりもやや淡いオリーブ褐色。腹部もオオヨシキリよりも淡い灰褐色だ。また、目の縁に眉斑があるのが特徴である。
生息環境はオオヨシキリと異なり、全国各地のよく茂ったササやぶなどで繁殖し、低地から高山まで広範囲に生息する。山地や寒冷地の個体は冬季には暖地に移動し、市街地の公園や庭先などでも姿が見られる。ちなみに、どちらもホトトギスやカッコウの托卵(たくらん)のタ―ゲットにされる野鳥である。
近年、農家の後継者不足から里山にも休耕田や放棄水田が増え、田んぼがヨシ原に変わりつつある。このままのペースで里山が荒廃していけば、春の訪れを告げるウグイスの美しい「ホー、ホケキョ」のさえずりを聞けなくなり、夏にオオヨシキリのやかましいさえずりだけが響き渡ることになるかもしれない。このような環境の変化は、生物多様性を損い、生態系にも大きな影響を与えかねないことから、私たち人間にとって決して好ましいことではないだろう。
(よな・しょうぞう=野鳥写真家、生駒市在住)=毎月第2、4月曜に更新
与名さんの写真集を正価より安くお求めいただけます
◇奈良高山の自然 茶せんの里の生きものたち(東方出版)
◇森のハヤブサ ナニワの空に舞う(東方出版)
→ ご案内はこちら