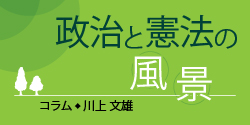コラム)気軽に立ち寄れる公民館に/川上文雄のじんぐう便り…19

自宅の庭に咲いた「ヘメロカリス」(和名、忘れ草)。撮影2025年6月25日
自宅から歩ける距離にある奈良市立平城西公民館の建て替えが決まり、それをきっかけに公民館に関心を持つようになりました。今までと違い、気軽に立ち寄れるようになれば良いと思います。「気軽に立ち寄れる公民館」、これは奈良市教育長の議会答弁のなかにあった語句です。みなさんはどんな公民館だったら気軽に立ち寄れそうですか。私の場合は、図書室かどこかに「大人のための絵本棚」のある公民館です。
絵本は子どものために読み聞かせるだけでなく、大人が自分のために読んで味わうこともできる(ノンフィクション作家の柳田邦男さんがそう言っています)。私のように歩いて行ける人は歩いて行き、「大人のための絵本棚」から1冊取って読んで、また歩いて帰る。絵本はゆっくりていねいに読んでも、そんなに時間がかからない(借りられるなら、借りてもいい)。気軽に立ち寄った公民館で読む絵本は、喫茶店で味わう一杯の飲み物のようなものかもしれません(ただし、こちらは無料)。
「気軽さ」は「絵本棚」を企画する側の人たちにとっても重要です。本棚の本は個人の寄贈または寄託によって集めることになるでしょう。ちいさな本棚1つ、その中の1段(の端っこ)からでよい。そうと思えば気軽に始められます。
本棚が少ないままでもいい。増えたとしても、図書室内に控えめに収まっている程度。やがて本に関わる他の市民グループの本棚が加わってにぎやかな図書室になり、老若男女を問わず多くの人が気軽に立ち寄ってくれる日を楽しみに待てばいい。
気軽に立ち寄って絵本を読んで楽しんでいるうちに、なにか違ったことをしてみたいと思うようになるかもしれません。私が思いつくのは、自分が持っている絵本のなかから選んで寄贈することです(これとは別に「好きな絵本と同じものを買って、それを寄贈する」もあります)。寄贈するなら、愛着のある絵本にしたいと思います。近所の、またはどこか別の公民館の図書室で、自分以外の誰かが読んでくれているかもしれないと想像するのは、とても楽しいことでしょう。
さらにその先、絵本を通じて自分が他の人々とつながる催しなどの場面が思い浮かびます。でも、絵本に限りません。生きがいを感じられることを、他人とのつながりのなかで一緒にやれたら、とても楽しいこと間違いありません。公民館には、そのための仕事でがんばってもらいたいです。本(絵本)について言えば、いろいろな地区の小さな図書室が連携してできることが何かあると思います。
冒頭でふれた「奈良市教育長の議会答弁」は以下のとおりです。
誰もが気軽に立ち寄れる仕組みづくりについては特に課題と捉えており、特定の利用者だけでなく幅広く多くの方々に利用していただける施設が望ましいと考えています。そのため、開放的な雰囲気づくりを目指して、例えば、図書室やロビーなどの、利用方法や雰囲気を見直すことで、誰もが気軽に立ち寄れる仕組みを醸成することで(課題の解決を)図りたい(2024年12月定例市議会)。
この答弁にあるように「気軽に立ち寄れる」は「開放的な雰囲気」があるということです。どのような図書室だったらそう言えるでしょうか。公民館の建て替え計画がない場合でも、図書室のあり方の再検討はできます。平城西公民館の場合は建て替えるので、建物の設計の全体計画のなかで「開放的な雰囲気」の図書室を考えることになります。
平城西公民館の設計について、重要な記述が奈良市公民館運営審議会「会議録(令和7年2月21日会議)」にあります。教育長その他で構成される「事務局」側の発言です。「公民館の設計については(土地造成とは別の)業者を選定したうえで教育委員会が主体的に関わる予定」(6ページ、https://www.city.nara.lg.jp/uploaded/attachment/195762.pdf)。どの程度主体的にやってくれるか注視したいと思います。
重要な記述がもう1つ「会議録」にあります。「(住民から)色んな形で意見を頂く機会をつくることが大事。間取りについての意見になると収拾がつかなくなってしまうが、どういった公民館にしたいのかというテーマであれば意見聴取しやすい」(6ページ)。
この箇所を読んで2つのことを思いました。1つは、「気軽に立ち寄れる(開放的な雰囲気の)公民館」をめざすなら「間取り」はとても重要だということ。そのつながりが確かにある意見は、ていねいに聴いていただきたいです。
もう1つ。「気楽に立ち寄れる公民館」と言っても、公民館は社会教育施設ですから、社会教育の基本をふまえた「気楽に立ち寄れる」ということだと思います。にわか勉強で「第4期(令和5年度~令和9年度)教育振興基本計画」(とりまとめ文部科学省総合教育政策局)を調べたところ、「社会教育を通じた地域コミュニティの形成」という語句が目に留まりました。参考として、「計画」の議論に参加した牧野篤さん(社会教育学)の言葉を紹介します。
(社会教育は)人々が日常生活において楽しい相互のかかわり合いの実践を生み出し続けることで、それぞれの人々の生活の目的が生まれ、地域コミュニティの目的がつくられ、そして社会の関係をつくり出すインフラストラクチャー(基盤)である(「アート×社会教育」34ページ、https://cs-wakasa.com/program/wp-content/uploads/2022/02/workbook2022_wakasa.pdf)。
(随時更新)

かわかみ・ふみお=客員コラムニスト、奈良教育大学元教員、奈良市の神功(じんぐう)地区に1995年から在住