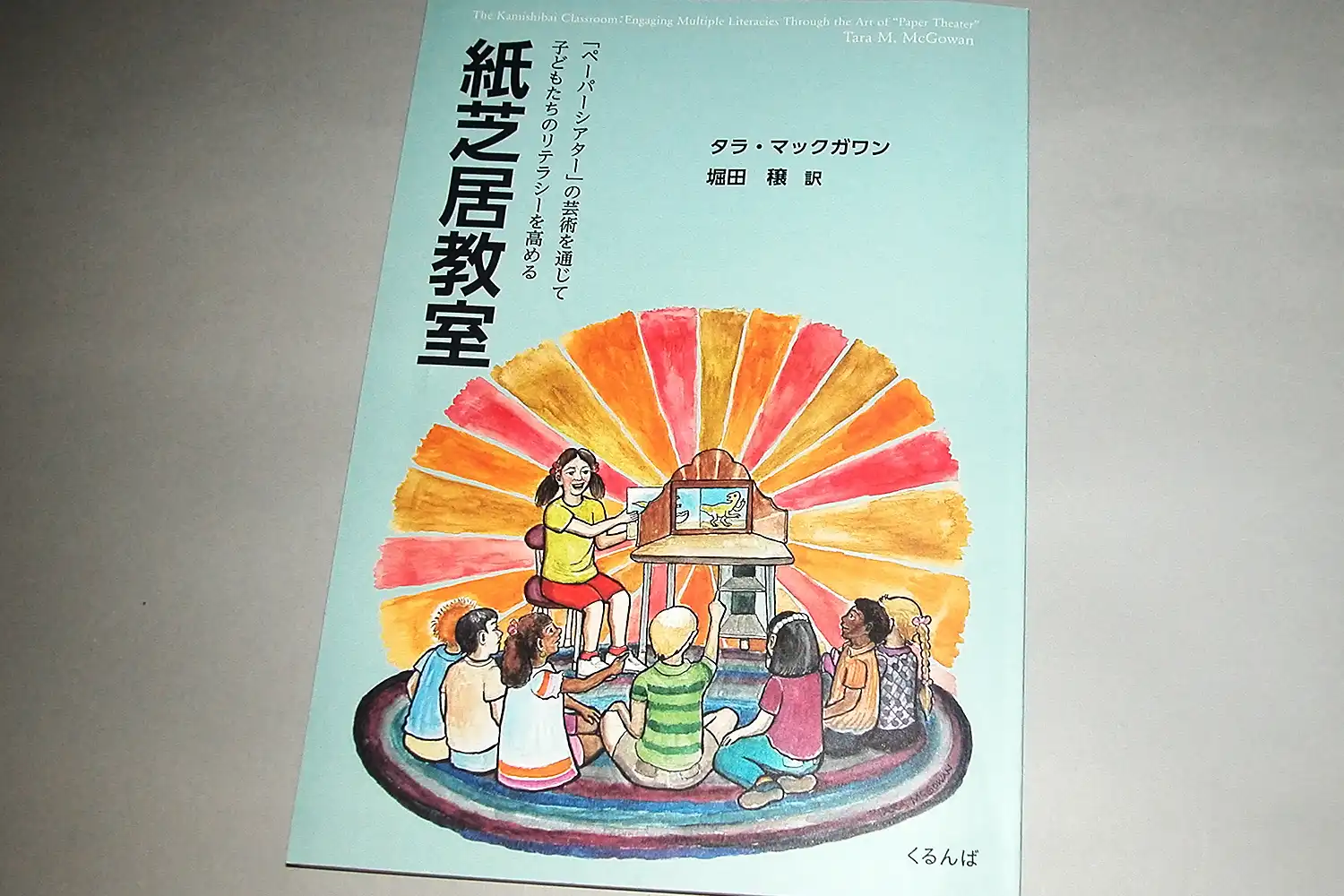奈良県立医大、ハラスメント相談を「悪意なし」と退ける 出産直前の女性医師に上司から連絡 出向いた帰りに転倒、帝王切開

奈良県立医科大学付属病院=2025年7月29日、橿原市四条町、浅野詠子撮影
奈良県立医科大学(橿原市四条町)の臨床教育の講座に所属し、同大学付属病院に勤務する女性医師が産前休業中の2022年1月、上司からの連絡で職場に出向いた帰りに転倒、緊急入院し、帝王切開で出産した。妊娠38周で出産直前だった。上司の対応は休業妨害に当たるなどとして、大学にハラスメント相談をしたが退けられた。
同大学のハラスメント防止規程に基づく相談員は医学部の管理職や大学企画部の管理職ら7人。うち2人が今回の相談員となり、調査結果は同年6月、人事課から対面で女性医師に伝えられた。内容は「上司に一切悪意はなく、すれ違いによるコミュニケーション不足に起因する思い込みが大きな要素を占めており、ハラスメントには当たらない」というものだった。
厚生労働省や自治体はハラスメント対策を講じるが、加害者の悪意の有無は必ずしも重要でないとされる。21世紀職業財団はホームページで「ハラスメントを行っている人も、悪意があるのはごく一部で、指導がうまくいかずつい強めに言ってしまったり、場合によってはその『つい』さえ認識していなかったりする人がほとんど」と警鐘を鳴らしている。
県立医科大学は、ハラスメント防止のために役職員らが認識すべき事項を定め、その中で「言動の受け止め方には個人差や男女差、その人物の立場などにより差があり、ハラスメントに当たるか否かは相手の判断が重要」としている。
大学は、女性医師から相談を受け、相談員のうち1人は女性医師との面談において「気のせいではないか」と感想を述べたという。
相談を受けた大学側が取りまとめた文書には、女性医師が訴えた転倒、破水、入院、帝王切開など、母子の安全が脅かされた事実への言及はなかった。また、労働基準法で認められている産前休業中に職場に出向かせたことも問題にされていなかった。
大学の規定によると、事実関係を調査する委員会を設置することができるが、それもなかった。
女性医師は、いくつかの疑問点について再質問したが、受付けられなかった。
大学人事課は「奈良の声」の取材に対し「個別のケースについての取材は応じられない」と話す。
◆ ◆ ◆
女性医師は当時、専門医取得のために研修中の専攻医。2022年1月5日、上司から、専門医試験を受けるために必要な書類が完成し「外来の机の上に置いてある」という連絡を受けた。連絡の意図は「書類を取りに来るように」という指示であると解し、出勤した。受け渡し方法については前年11月、出産を控えているため、秘書を通じ、書類は自宅に郵送してほしいと希望していた。
同大学付属病院の専攻医のほぼ全員が専門医を受験し、医局の指導責任者らが受験に必要な評価を記載する。女性医師が1月7日、病院の外来に評価票を取りに行くと、封入されず本人に対する評価が容易に見られる状態で置いてあった。評価票は「優良」「良」「可」「要努力」のいずれかを判定する箇所などがあり、女性医師の成績は良かったが、進んで第三者に見られたい情報ではなかった。
女性医師はこの後、徒歩で帰宅途中に橿原市内の路上でつまずいて転倒した。自宅で安静にしていたが、2日後の9日、上司からラインで連絡があり「社会人の常識として、重要書類の受け渡しは直接対面でなければならない。対面の受け渡しでない場合は、謝礼を対面で伝えなければならない」と諭された。
そして翌10日、破水し緊急入院、正常分娩ができなくなり、13日に帝王切開で出産した。薬剤の投与による陣痛や緊急帝王切開などにより、母子の合併症リスクは決して低くない状況にあったと見られる。上司から謝罪や見舞いの言葉はなかったという。
女性医師はその後、育児休業に入ったが、連絡などを巡って上司の対応の一部に疑問を感じた。医局の教授(退職)に相談したところ「話し合いで解決することは難しいだろう」との見解が示されたため同年3月、同大学人事課に「ハラスメントのご相談」との件名で相談内容を詳述した電子メールを送った。
これを受け大学の相談員は5月、女性医師と面談、同月から6月にかけ、上司ら2人と面談し、女性医師からの申し出内容の確認などをした。
その調査結果の文書を示すよう女性医師は人事課に求め、いったんは拒否されたが、しばらくして「メモ」と題された6月23日付の文書が調査結果に当たるとして電子メールで送られてきた。
これによると、産休前後の職員への配慮については、所属として注意すべきこととし、病院長が上司に対し「女性医師の職場復帰に際しては十分配慮するよう」指導していた。上司が、女性医師の個人情報が書かれた書類(評価票)を置いた場所はスタッフしか入れない場所で、書類は裏向きに置かれていたが、本人(上司)は「反省している」との記述があった。
その上で、大学側は上司に悪意がなく、すれ違いによるコミュニケーション不足に起因する思い込みがあったとした。
女性医師は納得できず、復職後の環境改善を求めたが「大学病院は介入しない」と告げられた。
そこで2022年9月、厚労省奈良労働局雇用環境・均等室に対し、再発防止に向け、労働施策総合推進法に基づく大学側との紛争解決への援助を申し立てた。同室は大学側の相談員に事情を聞いたが、「申立人(女性医師)にだけ再度、相談員が説明すると、他の人と不公平になる」などとして応じなかった。
解決が見込めそうにないことから、女性医師は同室に対し援助を打ち切ることを了承した。その際の同室の紹介で、10月、紛争当事者の一労働者として同じ労働施策総合推進法に基づくあっせん申請を同労働局に行い、さらに12月には調停申請を行い、上司や相談員ら3人の謝罪を求めた。しかし、大学側は多忙を理由に話し合いの席につかなかった。
医大労組にも相談した。労組は、女性医師との話し合いに応じるよう大学と交渉してくれたが進展しなかった。ただ、女性医師のハラスメント相談の内容が、本人が望まない形で一部職員に漏れた疑いがあったことから、守秘義務違反で公益通報することを勧める労組幹部もいて、これが一つのきっかけになって公益通報に新たな望みを託した。
女性医師は2023年1月、「大学はハラスメント防止規定に沿った対応をしておらず、労働施策総合推進法などに違反する」として大学に公益通報した。
しかし、パワー・ハラスメントは労働施策総合推進法で規定されているものの、刑罰または過料につながる法令違反行為とされていないことから、公益通報の通報対象に該当しないとされており、大学側はこれを理由に受理しなかった。
奈良県は今年2月、兵庫県庁で起きた公益通報者の保護問題などを踏まえ、通報者が従来の通報窓口の人事課だけでなく、委託した弁護士事務所にも通報できるようにした。
県人事課は「本県の公益通報窓口にハラスメントの通報があったことは近年、把握していない。通報者が深刻にハラスメントを訴えているのだとしたら、相談窓口に差し戻し、必要に応じて再調査し、場合によっては処罰することも検討されてよい」と話す。
女性医師は、公益通報をした2023年、育児休業から復職した。職場では別の上司から、緊急呼び出しに対応するオンコールを打診され、退職勧奨ではないのかと悩んだ。
大学の「女性研究者・医師支援センター」にハラスメントに当たると相談した。上司は同センターの聞き取りに対し、「口頭でオンコールを打診をしたところ、『子育などで対応できない』と断られ、やらなくていいと伝えた」などと回答。同センターはハラスメントの訴えを退けた。
その前年(2022年)、ある民間企業が全国の医師734人に対し行った調査によると、半数以上がハラスメントを経験していた。原因について、多忙で余裕のない環境を指摘する医師が相当数いた。
厚労省は「ハラスメントは、受け流しているだけでは状況は改善されない。『やめてください』『私はイヤです』と、あなたの意思を伝えよう」と啓発する。
一方、女性医師は「奈良の声」の取材に対し「やれることはすべてやったが、厳しい結果となった。今も納得がいかない」とし、ハラスメント相談の在り方やその調査結果に対し異議申し立ができる制度が必要と訴えた。
「奈良の声」は7月31日、女性医師の上司に対し取材申し入れの文書を郵送したが、8月24日までに返事はなかった。
筆者情報
- ジャーナリスト浅野詠子
- 電話 090-7110-8289
- メール info@asano-eiko.com
- ツイッター @asano_eiko