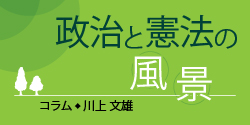コラム)飲酒運転に「危険運転罪」つくれ/川上文雄のじんぐう便り…17

さをり織りのコースター
多量に飲酒して自動車を運転、またはすさまじいスピードで運転して、対人の死傷事故を起こした。当然「危険運転致死傷罪」で裁かれる。私たちの常識はそう考える。でも、そのような事故の多くについて、検察は「過失運転致死傷罪」で起訴してきた。2つの「罪」が科す刑罰に極端な落差があり、きわめて軽い刑罰の判決になる。被害者・遺族が強い不満をいだくのは当然です。
この現状を変えるには、どうすべきか。「過失運転致死傷罪」の適用を断つことです。そのための法律改正案を考えました。ただし「飲酒運転」限定の改正で、飲酒運転の厳罰化を進めるものです。法律改正は法制審議会(法務大臣の諮問機関)でも検討が始まりましたが、それとはかなり違った改正案です。
提案は以下のとおりです。
(1)飲酒運転は事故(人身事故を含むすべての事故)を起こさなくても「危険運転罪」とする新たな法律を制定。現行の「酒気帯び運転」「酒酔い運転」より重い刑罰を科す。(現行の条文は廃止)
(2)現行の「危険運転致死傷罪」(危険運転罪よりも厳罰)は残す。(補足の説明は後述)
(1)と(2)により、飲酒運転による致死傷事故の場合、過失運転致死傷罪での起訴がなくなり、すべて危険運転致死傷罪での起訴になります。なお、飲酒運転以外では過失運転致死傷罪は残り、危険運転致死傷罪との「二本立て」という枠組みが残りますが、これは今後の検討課題とします。
厳罰化を進める私の改正案が広く社会的合意を得るためには、どのような考え方にもとづいて提案するのか、根拠を示す必要があります。被害者・遺族への同情だけでは足りません。
根拠は「道路は公共空間である。したがって、その上を走行する自動車運転は公共的な行為であり、それにともなう重い責任がある」。これは、飲酒運転以外の危険運転についても基礎的な考え方として有効だと思います。
それでは、道路とは何か。第1に、誰もが使える公共空間(ただし自動車の運転には免許が必要)です。ということで「誰か特定の人の所有物でない」から、誰も自分勝手には使えない。
誰もが使える道路。だから、その上をさまざまな人たちが同時に移動している。基本は運転者と歩行者(たいがいの人は「ある時は運転者、ある時は歩行者」)。障害のある運転者・歩行者、さまざまな年代の人たち。
その人たちの生活のほとんどすべての要素―穏やかな日常、買い物、冠婚葬祭、旅行、入学試験、よろこび・悲しみ、幸せになろうとしておこなうこと―は、道路を使って移動することにむすびついている。公園・広場とおなじく公共空間だけれど、それらとは比較にならないほど、生活の根幹をなしている。道路は道路網。それは、人体にたとえれば循環器系(血管、その他)でしょうか。
安全な公共空間としての道路は、そのように生活の根元を支える。憲法の言葉を使うなら「健康で文化的な生活」(25条)を支える。基本的人権の1つです。
さらに道路とは何か。「強者と弱者」の区別が、その上を移動する人たちのあいだにある。他人を傷つける「能力(可能性)」において運転者は圧倒的な強者。歩行者は弱者。ただし、運転者も道路を歩くことがあり、そのときは「弱者」です。
そこに飲酒運転者が現れたら? 飲酒運転者は最大の強者です。歩行者だけでなく、交通法規を守って運転している人も「弱者」になってしまう。暴力的な運転によって、公共空間が危険地帯に一変する。
そもそも自動車の運転者には「強者」としての重い責任―運転に関わる注意義務―がいろいろある。そのなかでも「飲酒運転しない」はとりわけ重いもの。この注意義務が求められるのは、「公共の福祉」(安全な公共空間としての道路を享受する権利)を理由としています。
運転免許も以上の視点で理解すべきだと思います。一定水準の運転技術(能力)を認定されて、道路上を自動車で走行する「許可」を得る。でも、それだけでは「免許とは何か」の半分に過ぎない。運転者に公共的な責任(基本的人権の尊重)を求める。それを前提として免許は与えられる。だから、免許によって手に入れるのは「権利」というより「資格」に近い。その点で、医療技術に関わる医師免許(資格)などに似ています。
飲酒したのに、うっかり運転してしまった。それを認めるなら「過失」犯罪かもしれない。現行の「酒気帯び運転」「酒酔い運転」の罰則のままでいいでしょう。しかし「単なる過失」(医師の場合なら「飲酒して、ついうっかり手術ミス」)にしたくない。「うっかり飲酒運転」は通用しないという社会的合意が存在する時代になっています。
その「合意」をふまえて、現行法規の枠組みを変えずに刑罰だけ重くするのではなく、新しい名称で「(飲酒)危険運転罪」と呼び厳罰を科す。冒頭の提案のとおりです。なお、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」をどのような基準で判断するのか。より厳しく判断するのか。それは今後の検討にゆだねます。
新しい犯罪名で呼ぶことの力。「家庭内暴力」という言葉の場合に似ています。いままでなかった言葉が使われるようになって、人々はその真実の姿(暴力に他ならない)を理解できるようになり、深刻な問題であると気づき、ものごとの基本を問い直すきっかけになったのと似ています。危険運転は暴力(狂暴)運転に他ならない。
一般常識とかけ離れた現行法規の運用に問題があることは、冒頭に書いたとおりです。さすがに「法制審議会」が危険運転致死傷罪について改正作業を始めています。「道路とは何か、自動車運転とは何か」の原点をふまえた検討を期待しています。しかし、検討は「運転技術」の視点から「制御できないレベルの速度超過運転とか飲酒運転とかを判断する数値基準を決める」ことが焦点になりそうなのが気がかりです。数値基準は必要。でも、それだけでは不十分だと思います。
(随時更新)

かわかみ・ふみお=客員コラムニスト、奈良教育大学元教員、奈良市の神功(じんぐう)地区に1995年から在住