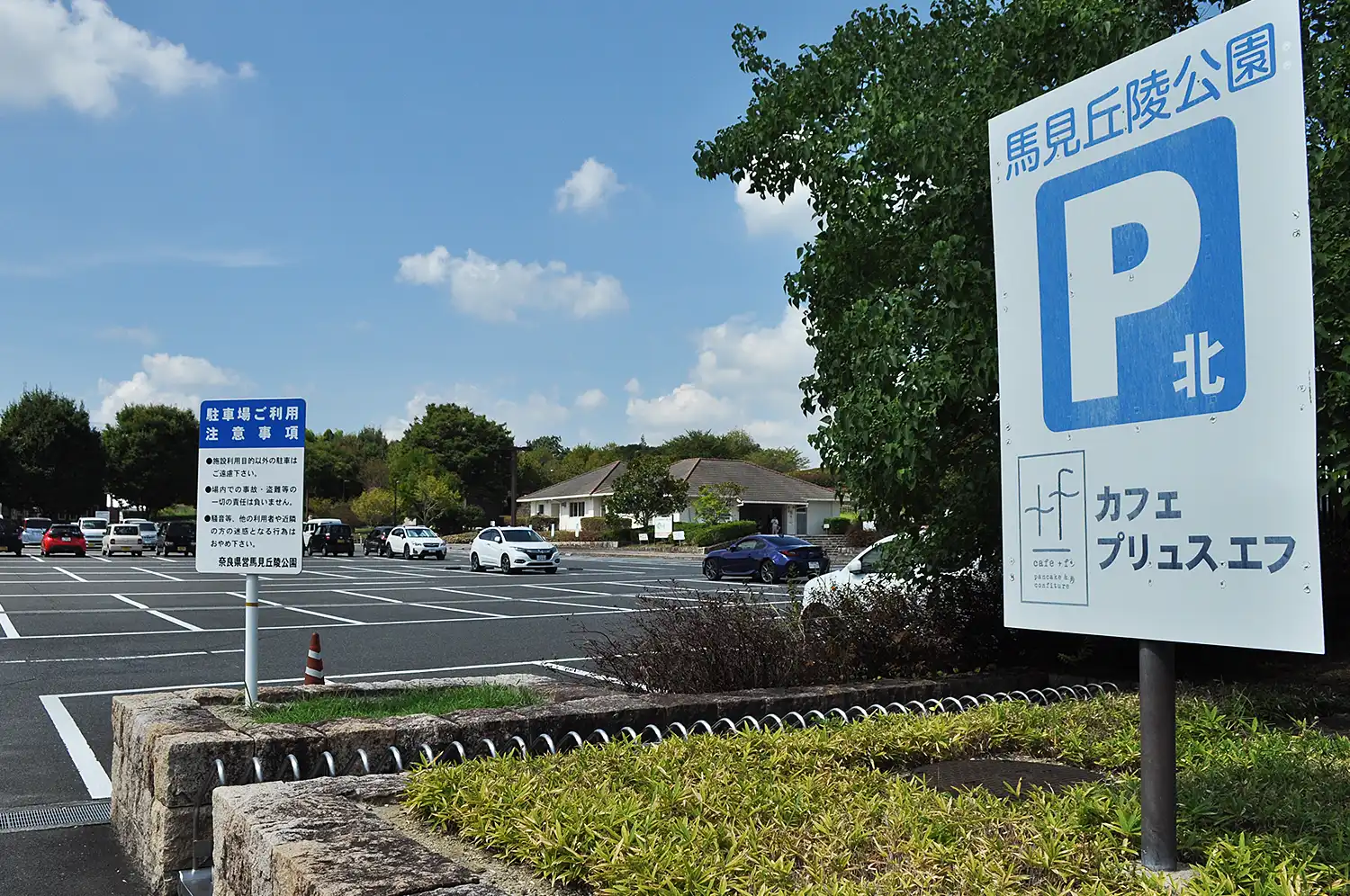視点)奈良県平群町のメガソーラー裁判から見える治水の争点 地裁が県基準容認 住民側控訴

森林が伐採されたメガソーラーの建設現場=2025年3月31日、奈良県平群町、浅野詠子撮影
奈良県平群町内の大規模太陽光発電(メガソーラー)計画に反対する地元住民が工事の差し止めや県の許可の取り消しを求めた訴訟の判決が3月25日、奈良地裁(和田健裁判長)であった。地裁は県の許可基準を容認し、訴えを棄却。住民側は4日、大阪高裁に控訴したが、裁判を通して大和川流域の治水が争点として浮かび上がっている。
平城宮跡の面積の約4割に匹敵する48ヘクタールの広大な山林に4万数千枚といわれるソーラーパネルを設置する民間会社(本社、東京都港区)の事業。直下の流域に住宅地がある。
県の防災基準は1982年の大和川豪雨災害を契機として策定された。降り始めから10時間の雨量150ミリを想定した調整池の設置などを業者に指導している。
これに対し住民側は、洪水調節容量の算定に行政が用いる「厳密計算法」を用いて「降雨が10時間を過ぎると、調整池があふれる恐れがある」と主張。住民たちは現地で観察を続ける。昨年3月下旬には、調整池の堰堤(えんてい)に亀裂が走り、「土の崩落を確認した」と裁判で訴えた。同月26日に降った雨(1日雨量50ミリ、時間最大145ミリ、奈良地方気象台観測)によるものと住民側は主張する。昨年の能登半島豪雨災害をはじめ、近年、各地で10時間・200ミリの雨量がもたらされていることから、県の防災対策を批判し、県が行った許可の取り消しを求めてきた。
古事記にある「くまがしの森」に当たるという。記者は2024年、2度にわたった住民説明会を傍聴した。住民の発言からは、古里の森林を侵食する巨大太陽光発電はやめてほしい、との願いが伝わってきた。
林地開発指導を担当する県森林環境課、治水を担当する県河川整備課の主張を聞くと、住民側の主張と真っ向から対立している。「森林法の規定では、開発前より流量を増やさないよう、30年確率の治水対策を義務付けられているが、これに加え本県は1960年代後半から採用しているゴルフ場開発基準を踏まえ、開発地より下流の地点にある水路のボトルネック(狭い地点)を勘案して指導していることから、森林法が求める以上の防災指導をしてきた。高裁では従前の主張を続けることになるだろう」と話す。
住民の憤りが一気に強まったのは2021年、メガソーラーの開発申請に誤りが見つかったときだ。反対住民の中心メンバーの一人で工業大学の土木工学科を出ている会社経営、須藤啓二さん(現在は町議会議員)が、計画地の下流河川の勾配が実際は7%程度なのに、それよりはるかに急な勾配の18%と書かれていることを発見した。
当時、ソーラー開発中止を求める住民の集まりで須藤さんはこう指摘していた。
「すごい勾配が書かれていて、例えばスキー場であれば、よほど熟達者でない限り滑走をためらわれるほどの斜面が計画地の流域に存在すると、申請書に出ていた。私は工学部の科目の中で河川工学が一番苦手だったが、そんな私でも、現地に立って観察すれば、うそがすぐ分かった。勾配がきつければ、豪雨の際に流下能力が高いとみなされ、その分、調整池の造成工事が少い金額で済む。これは何かある。おかしいと思った」
県の開発審査の担当者は現地で何を見てきたのだろうか。住民から指摘を受けた県は、いったんは工事の中止命令を出したものの、業者側が申請をやり直し、2023年、工事が再開された。
25年前のゴルフ場開発訴訟も治水が争点
所変わって吉野川流域のゴルフ場開発を巡る訴訟で、開発の差し止めを命じる判決が奈良地裁葛城支部で1999年3月、言い渡された。当時の県の防災基準では、調整池を設けても、雨の程度によれば奥六田川の下流などがあふれ、人々の生命を脅かす恐れがあると判決は指摘した。裁判では和歌山大学工学部教授だった宇民正さん(水理・河川工学)らの意見書が採用された。
現実の水路は微妙に複雑に蛇行したり、ときには土砂や流木が混ざったりしていて、計算上の流下能力が保たれるとは限らない。また、降雨はいつも都合よく調整池に入ってくれるわけではない。
こうしたことから国の河川管理施設等構造令は、計画高水流量に対し、「余裕高」を想定し調整池のサイズを決めるよう要請していたが、ゴルフ場開発業者は順守していなかった。今回、平群町のメガソーラー計画が下流河川の勾配を巡る問題で開発申請のやり直しとなったことは、県の開発指導の在り方をあらためて問うものだ。
再エネ特措法と河川法の座標軸
平群町の住民ら有志でつくる「平群のメガソーラーを考える会」は3月28日、「町の未来の子どもたちのためにも持続可能な環境を残したい」と声明を出し、電子メールなどを使って、切実な思いを知人から知人へ、一人でも多くの人に届けてほしいと呼び掛けた。
反対住民が不信感を持っていることの一つに、再生エネルギー特措法がもたらした電力の高価格買取り制度がある。「買取り期間が15年として180億円ほどの利益が出るそうだ。15年後、操業地の環境保全や流域の治水は一体誰が責任を持つことになるのだろう」と話す住民も。
2011年の東日本大震災の原子力災害発生後に、当時の民主党政権がかじ取りをした政策だ。高価格の固定価格買取り制度(FIT法)によって、電気料金に上乗せられ、国民負担が増大した。その対策としての改正FIT法施行では、2017年3月31日までに電力会社と接続契約を締結していなかった場合、現在のFIT法に基づく認定が失効する。
県内で巨大太陽光発電計画を巡って同じ問題を抱える平群町と山添村の住民が合同で開いた反対集会では、両町村の住民が励まし合ったこともあった。山添村では水道水源の山林に広さ81ヘクタールものメガソーラーが計画された。経済産業省近畿経済産業局エネルギー対策課によると、開発業者は2023年4月1日以降をもってFIT認定が無効となった。
村の担当課長の話では、ソーラー開発の事務所は引き払われている。現在は開発が止まっているように見えるが、すでに相当な面積の山林が買収されており、「今度は何が来るのか」と村民の心配はやまない。
「平群町は財政難なのに、どうして文句を付けるのか」と、メガソーラーの住民説明会について報じた「奈良の声」の記事に猛然と抗議する電話もかかってきた。今日は、財政の数値の健全化が至上命題になることがある。一方、地域の森を健全に保全すれば自治体財政が増収となる「森林交付税」の創設を真剣に提唱する首長が現れたこともある。
治水、水道水源のいずれも流域の「水」と関わっている。大和川豪雨災害の時代と比べ、災害は劇甚化し、その上、再エネ特措法という施策が森林伐採を誘導してしまった。
健全なコミュニティーの堅持こそ防災の要ともいわれる。平群町の流域治水の在り方を巡り、住民側と県はいまのところ妥協する気配はない。住民参加の手法を盛り込むことが可能な河川整備計画(河川法)にも視野を広げ、高裁での審理を見守りたい。